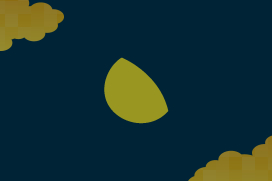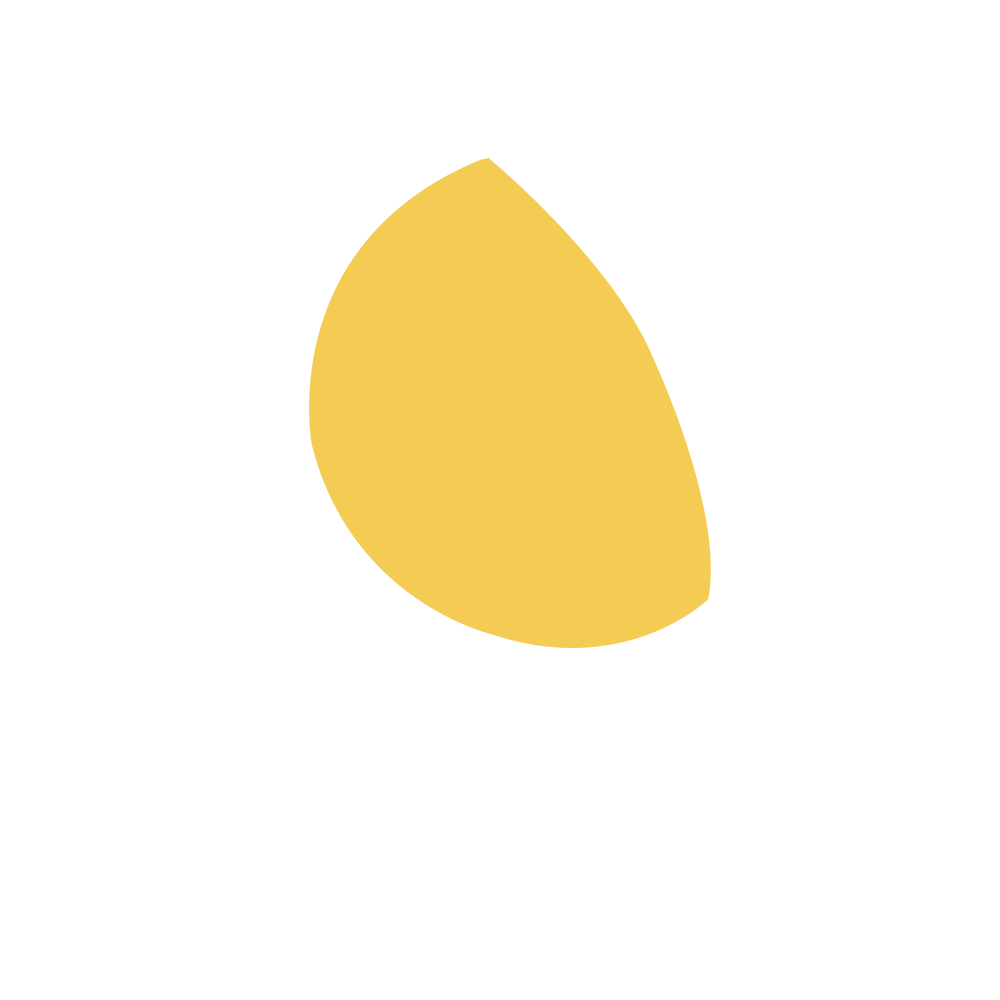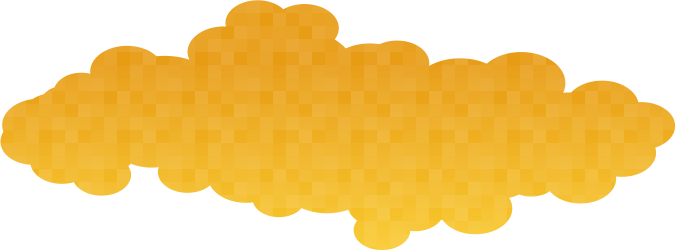
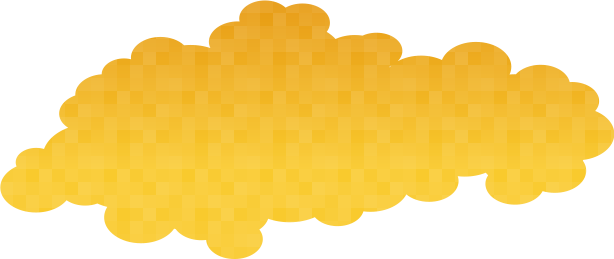

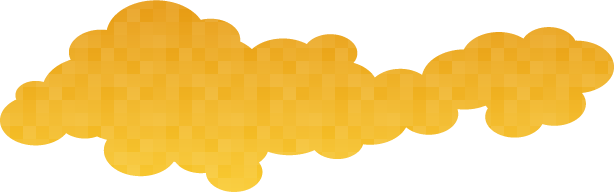
プレスルームPRESS ROOM

酪農学園大学×「そらとしば」産学連携プロジェクト始動
北海道北広島市「エスコンフィールドHOKKAIDO」球場内に所在するクラフトビール醸造レストラン「そらとしば by よなよなエール」と、酪農学園大学(所在地:江別市 学長:岩野 英知)は、北海道の食の未来を盛り上げるため、産学連携プロジェクトを始動します。同大キャンパス内で学生が育てた道産ライ麦を使用したクラフトビールを醸造し、6月上旬ごろから「そらとしば by よなよなエール」で提供します。また、クラフトビールのペアリングフード開発も行います*。
*ペアリングフードの商品化は未定です。
産学連携プロジェクト 酪農学園大学の2ゼミと共創
本プロジェクトのきっかけは、「日本の食や農の未来を担う学生たちに、農場で生まれた原料が消費者の食卓に届くまでの一連の流れを体感してほしい」という思いを持つ酪農学園大学からお声掛けいただいたことです。球場内で醸造から提供までを手がける「そらとしば by よなよなエール」として酪農学園の思いに共感し、プロジェクトを始動しました。「ライ麦を使用したビール醸造」「ペアリングフード提案」の2つの取り組みを通じ、原料が製品となりお客様に届くまでの流れを学生の方に体験いただく予定です。また、本プロジェクトを通じて、酪農学園大学の取り組みやクラフトビールの多様さを普段とは違う切り口で発信していくことで、産学の垣根を超え北海道の食やクラフトビール文化を盛り上げていきたいと考えています。
希少な道産ライ麦・ライ小麦を使用した限定クラフトビールを醸造 6月ごろ提供
ライ麦栽培の現状
北海道の寒冷な気候は、耐寒性の強いライ麦の栽培に向いています。また、ライ小麦は小麦とライ麦の雑種で収穫量が多く、小麦やライ麦と異なる風味をもっています。一方で、国産ライ麦・ライ小麦の生産はまだ盛んではなく、食用ライ麦の大部分は輸入に頼っているほか、ライ小麦については一部研究機関での栽培のみにとどまっています。また、日本においてライ麦・ライ小麦は肥料や飼料として使用されることが多く、食用としての用途はパンやクッキーなどのごく一部に限られているのが現状です。小麦の栽培が不安定な地域において、ライ麦・ライ小麦の食品への活用推進は、寒冷地の農業振興の一助となり得ます。
本取り組みの概要
「そらとしば by よなよなエール」は、酪農学園大学 循環農学類 作物学研究室の学生らが育てたライ麦・ライ小麦でビールを醸造し、レストランで提供します。国産ライ麦・ライ小麦を使用したビールづくりはまだ珍しく、普段ライ麦に触れることのない方にも食用ライ麦・ライ小麦を知っていただく機会となると考えています。学生と協力しライ麦の可能性を提案することで、北海道内の地に合う食用ライ麦・ライ小麦の普及を推進し、輸入に頼りがちな麦類の食糧自給率の改善を応援します。
なお、ライ麦・ライ小麦を使用し醸造したクラフトビールは、様々な味わいのビールを期間限定で醸造する「そらとしば シーズナル」シリーズとして、6月上旬ころから提供予定です。また、学生の方にはクラフトビールの醸造工程の一部を体験いただく予定です。
作物学研究室(義平大樹教授)
人類生存に不可欠な穀物(ムギ、マメ、トウモロコシ類)の良質多収栽培法の開発をテーマに研究。
パン用として栽培しやすいライ麦短稈品種の開発やライ小麦の新たな活用方法の研究に取り組んでいる。
研究室詳細:https://www.rakuno.ac.jp/archives/teacher/9320.html
●コメント
「学生たちは、研究上栽培に携わった作物が、副産物としてどのように活用でき、どんな価値を持つのかを実感できる機会は少ない。今回の取り組みを通じて、将来、農業関連産業の担い手となる学生たちに『栽培した作物がどのように加工利用され、消費者に届くまでの流れ』を肌身で感じる貴重な経験となれば、とても嬉しい。」
クラフトビールのペアリングフードを学生が提案 6月には学生によるプレゼンを実施
酪農学園大学 食と健康学類 栄養教育学研究室の学生に、クラフトビールに合うペアリングフードを提案いただきます。5月2日(金)に学生向けのオリエンを実施しペアリングの基礎を伝授、1.5か月の開発期間やフィードバックの機会を経て6月20日(金)に実際のフードをもとにプレゼンをしていただく予定です。
当初、酪農学園大学との取り組みは「ライ麦・ライ小麦のビール使用」のみを想定していましたが、原料の提供・使用だけでは「産学の垣根を超え、北海道の食を盛り上げたい」という共通の思いが果たせないと考え、栄養教育学研究室との連携にいたりました。学生の方には、「そらとしば by よなよなエール」らしい産学連携の取り組みを体験いただき、双方向での連携・共創を目指します。
栄養教育学研究室詳細(杉村留美子准教授)
食選択の決定を支援するための方法論を検討し、行動科学を用いてヒトの食行動がどのように変容するかを研究テーマとして、動機づけやスキルを高めるための栄養教育研究に取り組んでいる。
研究室詳細:https://www.rakuno.ac.jp/archives/teacher/9366.html
●コメント
「商品開発に興味をもつ学生は多く、しかも『エスコンフィールドHOKKAIDO』で販売されるチャンスをいただいた。今回は管理栄養士を目指す学生が集まり、ペアリングの学びから美味しさを考え、作業工程や原価などを考慮し、プレゼンに向けて試作を重ねる予定である。これら一連を経験できることは大変貴重な機会であり、有難い。」